「相続税って、お金持ちだけの話でしょ?」
そう思ってる人、実はめちゃくちゃ多いです。
でも最近は、都心のマンションや実家の土地だけでも課税対象になるケースが急増中。
「ウチは関係ない」と思っていたのに、
いざ相続の話になったら「えっ…相続税かかるの?」とあわてる人も少なくありません。
この記事では、
- 相続税ってどんな税金なのか?
- どんな財産にかかるのか?
- 「いくらまでなら非課税?」という基礎控除の考え方
など、知らないと損する仕組みをやさしく丁寧に解説していきます。
「まだまだ先の話」と思っている人にも、
“今知っておくことで将来のトラブルを防げる”ヒントが詰まってるので、ぜひ最後まで読んでみてください!
相続税ってどんな税金?
「相続税ってなんとなく聞いたことはあるけど、具体的にどういう税金なのか分からない…」
そんな人も多いのではないでしょうか?
✅ 相続税=“もらった財産”にかかる税金
相続税は、亡くなった人から財産を引き継いだときに発生する税金です。
「もらった側」に課税されるのがポイント。
財産をもらったすべての人にかかるわけではなく、
一定額を超えたときだけ発生する仕組みになっています。
✅ 財産って何が含まれるの?
- 現金・預金
- 不動産(土地・建物)
- 株式や投資信託などの金融資産
- 車や骨董品などの資産価値があるもの
- 死亡保険金(一部)
「え、これも対象なの?」というものまで含まれるケースもあるので注意が必要です。
✅ 相続税がかかるのは“受け取った人”の話
ちなみに、税金を支払うのは故人ではなく、
財産を受け取った側(相続人)です。
だから、いざ自分が「もらう側」になったときのために、
しっかりと知っておくことが大切なんです。
どんなときに相続税がかかるの?
「相続税って、実際にどういうときに払うことになるの?」
──答えはシンプルです。
相続した財産の“合計額”が、基礎控除額を超えたときに相続税が発生します。
✅ 基礎控除の考え方
相続税には、「この金額以下なら税金はかかりませんよ」という【基礎控除】があります。
その計算式はこちら:
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
✅ 例:相続人が2人の場合
3,000万円 +(600万円 × 2人)= 4,200万円
この場合、相続した財産の合計が4,200万円を超えると、相続税の対象になります。
✅ 家や土地でオーバーすることも…
「そんな大金ないから大丈夫でしょ」と思いがちですが、
たとえば親の住んでいた家や土地を相続するだけで、
評価額が数千万円になるケースも普通にあります。
預貯金が少なくても、不動産や保険などを含めると課税対象になることがあるんですね。
つまり、相続税は「現金持ちだけの話」ではなく、
“実家を相続しただけで対象になる”ような、身近な税金でもあるんです。
課税対象になる財産の種類は?
相続税は、現金や預金だけにかかるわけではありません。
実は、さまざまな種類の財産が課税対象になるんです。
ここで、よくある財産をわかりやすくまとめておきます。
✅ 課税対象となる主な財産
- 現金・預貯金
- 土地・建物などの不動産
- 株式・投資信託などの金融資産
- 生命保険金(※受取人によっては課税対象)
- 自動車、貴金属、宝石、骨董品など
- 貸付金・未収入金(貸していたお金)
✅ 非課税になるものもある
以下のような財産は、条件付きで非課税になります。
- 生命保険金(法定相続人 × 500万円までは非課税)
- 死亡退職金(こちらも法定相続人 × 500万円までは非課税)
- 墓地・仏壇・祭具など
✅ 見落としがちな「名義預金」や「生前贈与」
- 被相続人の口座に入っていたが、実は家族の資金だった「名義預金」
- 相続前の短期間に行われた「生前贈与」
これらも税務署にチェックされやすいポイントなので、注意が必要です。
つまり、相続税の対象となるのは、
「明らかに財産です!」というものだけじゃなく、
「価値があるもの」「形はないけど権利があるもの」まで含まれるんですね。
基礎控除の計算方法とポイント
相続税がかかるかどうかを決める基準になるのが、
この【基礎控除】という金額です。
✅ 計算式はこちら!
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
つまり、相続人の数が多いほど、非課税枠が広がります。
✅ 例で見てみよう!
たとえば、相続人が「配偶者と子ども2人」の3人だった場合:
3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円
この場合、相続した財産の合計が4,800万円以下なら、
相続税はかかりません。
✅ ポイント①:法定相続人の数がカギ
- 実際に相続した人の数ではなく、法律上の「相続人の数」で計算
- 相続放棄していてもカウントされる場合がある
✅ ポイント②:分割の割合は関係ない
誰がどれだけ相続したかに関係なく、
まずは「合計額」が基礎控除を超えているかどうかが判断基準です。
この基礎控除の存在を知っておくだけでも、
「え、これって相続税かかるの?」というモヤモヤがだいぶスッキリしますよ!
配偶者や子どもへの特例ってあるの?
「相続税って、全部にかかるわけじゃないの?」
──そうなんです。
実は、一定の条件を満たすと“相続税がかからない”ケースもあるんです。
ここでは代表的な「配偶者」「子ども」への特例を紹介します。
✅ 配偶者の税額軽減(超強力)
配偶者が相続する財産については、
次のどちらか少ないほうまで相続税がかかりません。
- 配偶者の法定相続分
- 1億6,000万円
つまり、1億6,000万円以内の相続なら、配偶者は“非課税”になるケースが多いんです。
✅ ポイント:申告が必要なので放置NG!(自動で非課税にはならない)
✅ 小規模宅地等の特例(自宅の土地が大幅減額に)
相続した自宅の土地については、
一定条件を満たすと最大80%評価減が適用されます。
例:5,000万円の評価だった土地 → 実質1,000万円扱いに!
- 被相続人と同居していた配偶者や家族が対象
- 一定の面積制限あり(330㎡までなど)
✅ ポイント:申告すればOK。申告しないと減額されないので注意!
✅ 教育資金・贈与との併用も可能
相続直前に行われた生前贈与などについても、
一定額までは非課税になる制度があります。
これらの特例をうまく使えば、
「実は課税対象だけど、相続税はゼロだった」というケースも珍しくないんです。
相続税を減らすためにできること
「相続税って避けられないの?」
「節税とかって、結局お金持ちだけの話じゃないの?」
──いえいえ、実は誰でもできる“備えと工夫”で、相続税を減らす方法はあります。
ここでは、実践しやすいポイントを3つに分けて紹介します。
✅ ① 生前贈与を上手に活用する
- 毎年110万円までの贈与は“非課税”(暦年課税の非課税枠)
- 時間をかけてコツコツ贈与することで、将来的な相続財産を圧縮できる
📌 注意:贈与と相続は「連動してチェック」されるため、形式だけの操作はNG
✅ ② 非課税制度をしっかり活用する
- 生命保険の非課税枠(500万円 × 法定相続人)
- 死亡退職金の非課税枠(同じく500万円 × 法定相続人)
- 小規模宅地の特例など、税制優遇は申告すれば適用される
📌 ポイント:非課税制度は“自動適用されない”ため、申告がマスト
✅ ③ 相続対策は“早めに・話し合いながら”が鉄則
- 「争族」にならないよう、家族で話し合っておくことが大事
- 遺言書や財産の棚卸しなど、元気なうちに準備できることはたくさんある
- 専門家(税理士・行政書士)への早期相談も◎
つまり、相続税は“ただ払うだけのもの”じゃなく、
「知って、備えて、減らせる」税金なんですね。
まとめ:相続税を知れば、未来の安心につながる
相続税と聞くと、「なんか難しそう」「うちは関係ない」と思いがちですが、
実は不動産や保険などを含めれば、意外と身近な問題だったりします。
この記事では、
- 相続税がどんなときにかかるのか
- 基礎控除の計算方法
- 特例や節税のヒント
まで、やさしく解説してきました。
大切なのは、「知らずに損する前に、ちょっと知っておくこと」。
今すぐ対策する必要がなくても、
知識があるだけでいざというとき「慌てず、迷わず、備えられる」ようになります。
相続は、お金の話であると同時に、
家族との関係や人生設計にも深く関わるテーマ。
だからこそ、「ちゃんと知ってる」ってだけで、
家族みんなの安心につながるんです。
この記事が、あなたの「なんとなくの不安」を
「納得」と「安心」に変えるきっかけになれば嬉しいです。



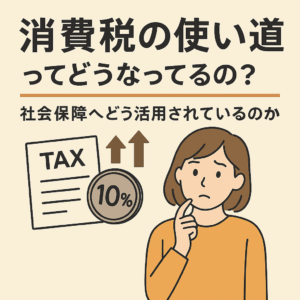
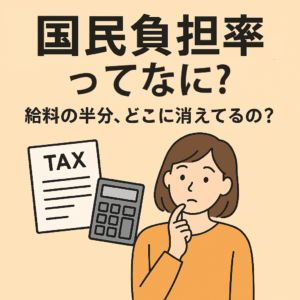
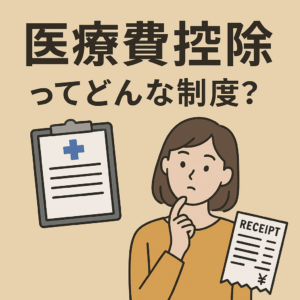
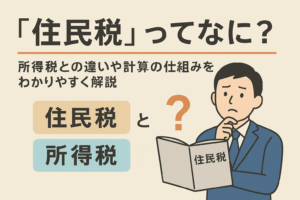
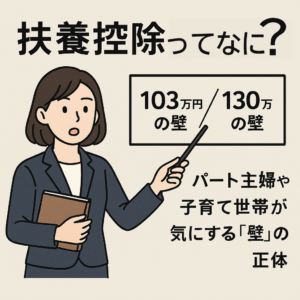
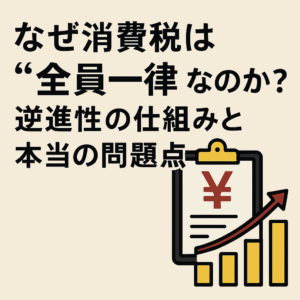
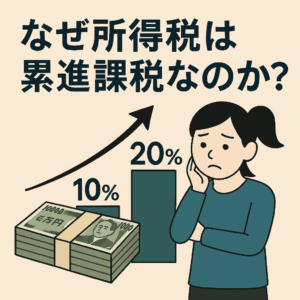
コメント