「病院行ったら“3割負担です”って言われたけど…これってどういうこと?」
診察や薬を受けたときに、
なにげなく支払っている「医療費の3割」。
当たり前のように聞き慣れているけれど、
よく考えると“残りの7割”はどこから来てるの?”“なぜ3割なのか?”って疑問、ありませんか?
この記事では、日本の医療費の自己負担が3割である理由、
そしてそこにある制度の仕組みや歴史的背景を、
専門知識ゼロでもわかるように、やさしく解説していきます。
最後には「高額療養費制度」や「年齢・所得による違い」など、
実生活に役立つ情報もあわせて紹介するので、
「医療費って高くない?」「損してない?」と感じたことがある人は、ぜひ最後まで読んでみてください!
医療保険制度の基本をおさらい
「医療費の3割負担ってどういうこと?」
──その答えを知るには、まず日本の医療保険制度の仕組みを理解する必要があります。
✅ 日本は“国民皆保険(かいほけん)”制度
日本では、すべての人が何らかの医療保険に入ることが法律で決められています。
これを「国民皆保険制度」と呼びます。
✅ 3つの代表的な保険制度
| 保険の種類 | 対象 | 管理者 |
|---|---|---|
| 健康保険(社保) | 会社員・その扶養家族 | 協会けんぽ・組合など |
| 国民健康保険(国保) | 自営業・フリーランス・無職の人など | 市区町村 |
| 後期高齢者医療制度 | 75歳以上の人 | 都道府県ごとの広域連合 |
✅ 「みんなで少しずつ出し合って、困った人を助ける」
医療費の自己負担が3割で済むのは、
残りの7割をこの保険制度がカバーしてくれているからです。
つまり、働いている人も、そうでない人も、保険料を支払うことで“助け合いの仕組み”に参加しているということなんですね。
この仕組みがあるおかげで、
私たちはいつでも安心して病院にかかれるというわけです。
なぜ自己負担が“3割”なのか?
「病院代って、なぜ3割だけ払えばいいの?」
「5割でもなく、1割でもなく、“3割”にした理由ってなに?」
──実はこの数字、ちゃんとした“根拠と狙い”があるんです。
✅ ① 過度な医療利用を防ぐため
もし医療費がすべて無料だったら──
「ちょっと喉が痛いから、とりあえず病院いこっか」と、
本当に必要かどうかを考えずに受診する人が増えてしまいます。
そうなると、病院が混雑し、医療費全体も増え続けてしまう…。
そこで「一定の自己負担(3割)を設けることで、“本当に必要なときだけ使う”意識を促す」という狙いがあるんです。
✅ ② 財政負担とのバランス
もし1割や無料にすると、国や自治体が負担する医療費が急増して、
保険制度そのものが持たなくなるおそれがあります。
逆に、5割負担では「医療を受けたくても受けられない」人が出てしまう。
その結果、「7割は保険、3割は本人が負担」という、
利用抑制と公平性のバランスを取った“中間の数字”として採用されたのが“3割”なんです。
つまり、3割という数字には、
- 📉 医療の使いすぎを防ぐ
- 💰 財政の健全性を保つ
- 🤝 誰もが医療を受けられるようにする
そんな3つの目的を両立させる絶妙なバランスがあるってことなんですね。
3割負担はいつから始まったの?
現在、一般的に「医療費3割負担」とされていますが、
実は最初から3割だったわけではありません。
この制度、少しずつ段階を踏んで今の形になってきたんです。
✅ 1984年以前:サラリーマンは“無料”だった!
驚くことに、かつての日本では、
会社員(健康保険加入者)は自己負担ゼロ=完全無料で医療を受けられました。
✅ 1984年:サラリーマンに“1割負担”導入
「医療費の増加が止まらない」との声から、
ついに会社員にも1割負担が導入されます。
✅ 1997年:2割負担へ引き上げ
少子高齢化が進み、社会保障費が膨張する中、
医療費のさらなる増加を抑えるために、負担率が2割に。
✅ 2003年:現在の“3割負担”に
そして2003年、ついに現在の「3割負担」へ。
これが、現代の基本的な医療制度として定着しています。
つまり、「3割負担」はいきなり生まれたわけではなく、
時代に合わせて“徐々に上がってきた”制度の結果なんですね。
年齢や収入で自己負担は変わる?
「え、うちの親は1割しか払ってないけど?」
「高収入の人って、もっと払ってるんじゃないの?」
──そんな声もある通り、医療費の自己負担は“全員が3割”というわけではありません。
実は、年齢や収入によって負担割合は変わる仕組みになっています。
✅ 一般的な自己負担の目安
| 対象者 | 自己負担割合 | 備考 |
|---|---|---|
| 0〜5歳 | 2割 | 一部自治体で助成あり |
| 6〜69歳 | 3割 | 一般的な負担割合 |
| 70〜74歳(一般) | 2割 | 所得に応じて3割になる場合あり |
| 75歳以上 | 1割または2〜3割 | 所得によって段階的に変動する |
✅ 所得が多いと負担も増える
とくに高齢者の場合、一定以上の年収があると“2割〜3割”に引き上げられます。
これは「負担能力に応じた公平性」を保つための仕組みです。
✅ 各自治体の助成制度もあり
子どもやひとり親家庭などに対して、
各市区町村が独自に助成制度(医療費無料など)を設けているケースもあります。
つまり、「みんな3割」というわけではなく、
年齢・収入・住んでいる地域によって医療費の負担額は変わるというのが実態なんですね。
海外と比較するとどうなの?
「日本の医療費3割負担って、世界的に見てどうなの?」
──これ、気になりますよね。
日本の医療制度って実は、“かなり優秀”とされている部類なんです。
🇬🇧 イギリス
- NHS(国民保健サービス)により、原則“無料”
- 医療は基本税金で賄われる
- ただし、医療体制が慢性的にひっ迫しており「予約が取れない」「待ち時間が長い」といった課題も
🇫🇷 フランス
- 原則7割を保険が負担、3割を自己負担
- 高額医療や慢性疾患については、さらに補助がある
- 保険の仕組みが充実しており「患者負担が実質ゼロ」のことも多い
🇺🇸 アメリカ
- 民間保険が中心。公的保険は限定的
- 保険未加入者は全額自己負担というケースも
- 医療費は世界最高レベルに高く、「医療破産」が社会問題に
🇯🇵 日本
- 自己負担は原則3割
- 国民皆保険で、誰でも安心して医療を受けられる
- 高額療養費制度もあり、“いくら使っても青天井”にはならない
こうして比較すると、
日本の医療制度は「やや負担はあるが、平等性と安心感のバランスが高水準」ということが見えてきます。
つまり、“ただの3割”ではなく、“安心して暮らせる3割”なんですね。
まとめ:医療費3割の意味を知ることが安心につながる
「なんで医療費って3割なの?」
そんな素朴な疑問の背景には、
日本の医療制度の工夫やバランスへの配慮がたくさん詰まっていました。
✅ おさらいポイント
- 医療保険制度があるから、自己負担は3割で済んでいる
- 3割という数字には、「使いすぎ防止」「制度の維持」「公平性」という意味がある
- 年齢や所得によって負担割合は変わる
- 海外と比べても、日本の医療制度は“安心して使える”バランス型
私たちは毎日のように医療制度に支えられて暮らしています。
でもその仕組みや背景を知らないままだと、
「高いな」「なんか損してない?」と感じることもあるかもしれません。
だからこそ──
知識を持つことで、安心して制度を活用できる。
そしてそれが、将来の医療や社会保障について考える第一歩にもなります。
この記事が、あなたの「モヤモヤ」を少しでも晴らし、
“納得して支払える3割”への理解につながったなら、嬉しいです。

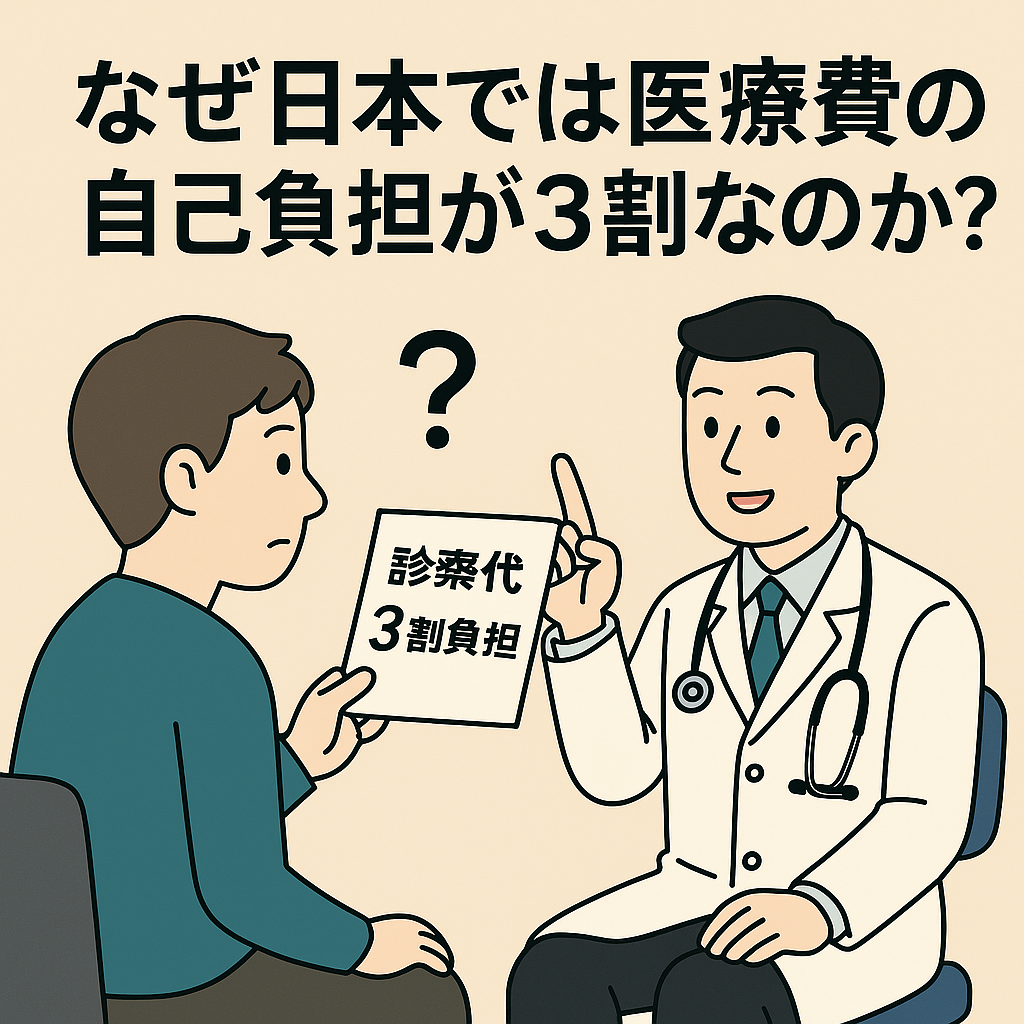

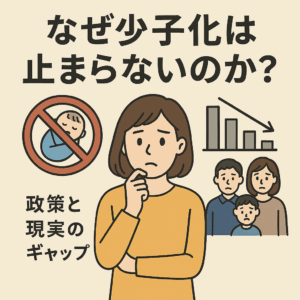

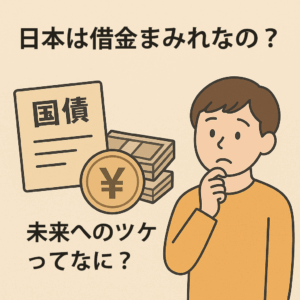

コメント