「病院代けっこうかかったけど、どうにもできないよな…」
「医療費控除って聞いたことあるけど、正直よくわからない」
そんなふうに思っていませんか?
実は、年間の医療費が一定額を超えた場合、確定申告をすることで税金の一部が戻ってくる制度があるんです。
でも、「知らない」「難しそう」という理由で、毎年スルーしてしまう人がとても多いのが現実。
この記事では、
- 医療費控除ってなに?
- どんな費用が対象になるの?
- いくら戻ってくるの?
- どうやって申請すればいいの?
などを、できるだけやさしく・具体的に解説していきます。
✅ 医療費控除は、“使える人は絶対に使った方がいい制度”です。
この記事を読めば、損せずにお金を取り戻すための一歩が踏み出せるはずです。
医療費控除ってどんな制度?
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、税金の一部が戻ってくる制度です。
✅ 具体的にはどういうこと?
- 本人や家族の医療費が【年間10万円(または所得の5%)を超えた分】について
- 確定申告することで【所得税・住民税が軽減】される仕組み
👉 控除額に応じて、還付金として現金で戻ってくる場合もあります。
✅ 控除の上限は?
- 控除対象の上限は【200万円まで】
- 所得が多い人ほど、戻ってくる税額も大きくなります
✅ ポイントは、
“医療費が高かったら、泣き寝入りしないで申告しよう”ということなんですね。
医療費控除の「対象となる金額」はどう決まる?
「医療費が10万円超えたら全部戻ってくるの?」
──実は、控除される金額には明確なルールがあります。
✅ 控除対象の算出式(基本)
(支払った医療費の合計)-(保険金などで補填された金額)-10万円(または所得の5%)※「10万円」ではなく「所得の5%」になるのは、所得が200万円未満の人の場合です。
✅ 具体例
- 1年間で支払った医療費の合計:30万円
- 生命保険からの給付金:5万円
- 所得:400万円(→控除対象ラインは10万円)
👉 控除対象額の計算:
30万円 − 5万円 − 10万円 = 15万円(これが医療費控除の対象)✅ ポイント
- 保険金や共済金などで補填された分は、控除の対象外
- 医療費がかかったからといって、全額が戻るわけではない
でも、控除対象が15万円なら、数万円単位の還付が期待できることもあります!
✅ 「実際に控除される金額」の仕組みを知っておくことで、
「どこまで取っておけば得なのか」が判断しやすくなります。
医療費控除で実際にいくら戻るのか?具体例で解説
「控除対象額はわかったけど…実際どのくらいお金が戻ってくるの?」
──ここでは、還付金のイメージが湧く具体例をご紹介します。
✅ ケース①:年収400万円・医療費30万円・保険給付5万円
- 控除対象額=30万円 − 5万円 − 10万円=15万円
- 所得税率:10%(年収400万円の人の目安)
👉 所得税の還付額:15万円 × 10% = 15,000円
さらに、住民税(約10%)も軽減されるため──
👉 住民税軽減:約15,000円 × 10% = 1,500円前後
※自治体によって異なります
✅ ケース②:年収600万円・医療費50万円・保険給付10万円
- 控除対象額=50万円 − 10万円 − 10万円=30万円
- 所得税率:20%
👉 所得税の還付:30万円 × 20%=60,000円
+ 住民税軽減:30万円 × 10%=約3,000円
✅ 注意ポイント
- 還付額は【課税所得・税率】により変動します
- 控除額=還付金ではないが、目安として「控除額の10〜20%が戻る」と考えてOK!
✅ 「そこまで高額じゃないし…」と思っていた人も、
数万円レベルで返ってくることがあるというのは意外と見落とされがちなんです。
どんな医療費が対象になるの?
「病院代って全部対象になるの?」
──そう思った方へ。実は対象になるもの・ならないものが、きちんと決まっています。
✅ 対象になる医療費(例)
| 分類 | 内容例 |
|---|---|
| 診療・治療費 | 病院の診察、治療、手術、入院費など |
| 医薬品 | 風邪薬、処方薬などの購入費 |
| 交通費 | 通院のための公共交通機関の費用(バス・電車) |
| 歯科治療 | 虫歯治療、歯周病治療、抜歯など |
| 出産・妊娠関連 | 妊婦健診、分娩費用、通院費、入院費など |
❌ 対象外の費用
- 美容目的の整形手術
- 健康診断(異常なしの場合)
- 自家用車のガソリン代や駐車場代
- 予防接種・サプリメント費用など
✅ ポイント:「治療目的」であれば、意外と広く対象になることも多いんです。
確定申告のやり方と注意点
「使えるのはわかった。でも、どうやって申告するの?」
──ここでは、医療費控除を受けるための手続きの流れと注意点を解説します。
✅ 申告の手順(ざっくり5ステップ)
- 1年間の医療費を集計する
→ 自分や家族の医療費のレシート・明細をまとめる - 「医療費控除の明細書」を作成する
→ 国税庁HPのフォーマット or e-Taxで作成 - 確定申告書に入力・添付する
- 税務署へ提出(郵送・持参 or e-Tax)
- 還付金がある場合は振込を待つ
✅ 注意点
- 医療費のレシートは1年間きちんと保管!
- 医療費通知(健康保険から届く明細)も有効
- 家族分をまとめて申告OK(生計一の場合)
✅ 申告時期は通常【2月中旬〜3月中旬】ですが、
還付目的だけなら1年中いつでも申請可能!
👉 「今年の分は無理かな…」と思っても、実は5年までさかのぼって申告できます。
セルフメディケーション税制との違いは?
実は医療費控除と似た制度に、
「セルフメディケーション税制」というものもあります。
✅ 簡単にいうと…
✅ 医療費控除:治療費など、病院にかかったときの費用が対象
✅ セルフメディケーション税制:市販薬の購入費が対象
✅ セルフメディケーション税制の条件
- 特定の市販薬(対象のOTC医薬品)を1万2,000円以上購入
- 自分自身が「健康診断などを受けていること」が条件
- 控除上限:8万8,000円
👉 医療費控除と併用は不可!
どちらか有利なほうを選ぶ必要があります。
✅ ポイント:「通院が少なくても、ドラッグストアでよく薬を買う人」は、
この制度のほうが向いていることもあります。
まとめ:医療費控除は“知ってる人だけ得する”制度
まとめ:医療費控除は“知ってる人だけ得する”制度
「なんとなく難しそうでスルーしていた」
「どうせ大した金額じゃないと思っていた」
──そんな人こそ、一度じっくり確認してほしいのが“医療費控除”です。
この記事では、
- 医療費控除の制度の仕組み
- 対象になる金額の算出方法
- 実際にどれくらいお金が戻るかの例
- 対象となる費用/対象外の費用
- 申請の流れと注意点
- セルフメディケーション税制との違い
をできるだけわかりやすく整理してきました。
✅ ポイントは、「知ってる人しか得をしない」ということ。
✅ 医療費がかかった年に確定申告するだけで、数万円レベルのお金が戻ってくる可能性もあるんです。
「ちょっと面倒そう…」と思っても、
- 医療費通知やレシートが手元にある
- 年間10万円以上使っていそう
- 自分や家族の治療が多かった年
こんな条件に当てはまるなら──
“損せずに申請”する価値、じゅうぶんにあります!
まずは、財布や引き出しに眠ってるレシートを
そっと取り出してみるところから、はじめてみませんか?💡

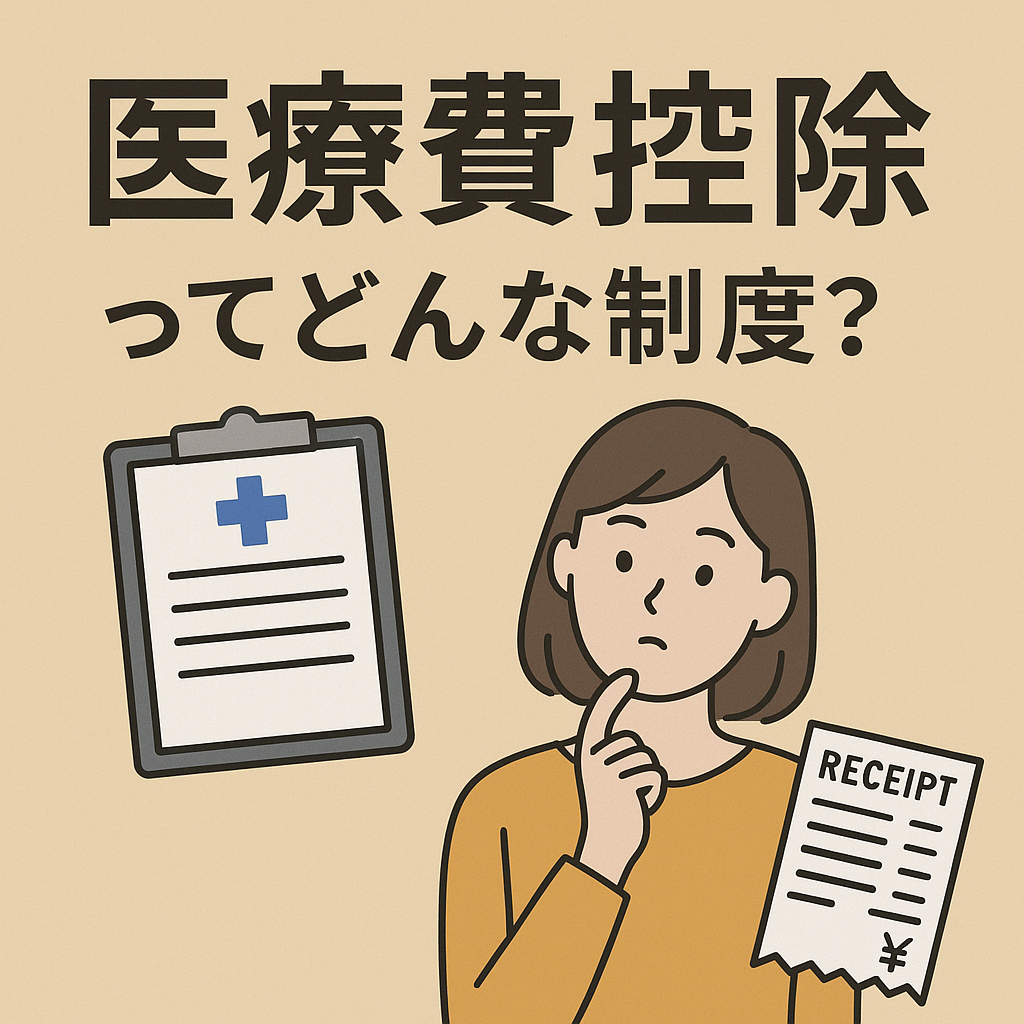

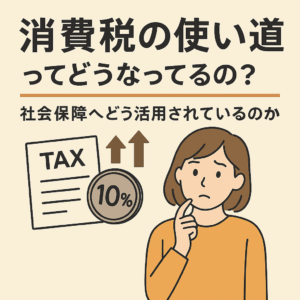
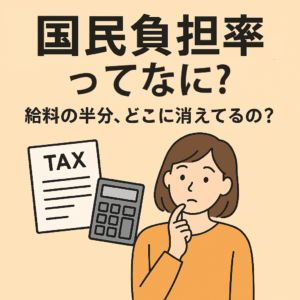
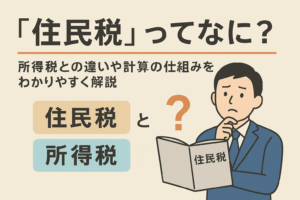
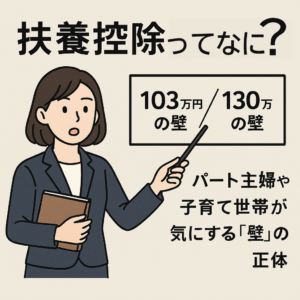
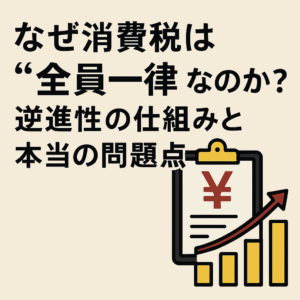
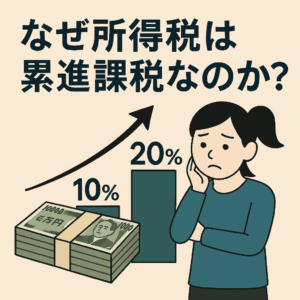
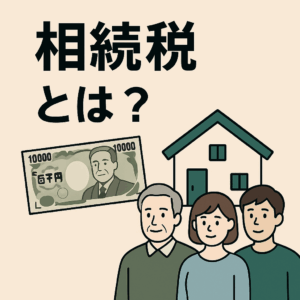
コメント