「住民税」ってなに?所得税との違いや計算の仕組みをわかりやすく解説
「住民税って、そもそもなんの税金?」
「なんで毎月引かれてるのか、正直よくわからない…」
そんなふうに感じたこと、ありませんか?
所得税と違って、“あとからまとめてくる”のが住民税。
しかも年によって金額が違ったり、「なんでこんなに高いの!?」と思ったり…
仕組みが見えにくい分、モヤモヤしやすい税金なんですよね。
この記事では、
- 住民税の基本的な仕組み
- 所得税との違いとは?
- どうやって金額が決まるのか?
- 払いすぎ・損しないための考え方
など、税金がニガテな人でもスッと理解できるように解説していきます。
読めばきっと、
「住民税の通知が怖くなくなる」──そんな感覚を得られるはずです。
住民税ってどんな税金?
住民税とは、簡単に言えば、
「自分が住んでいる自治体(市区町村・都道府県)に納める税金」のことです。
✅ 住民税は“地域のため”の税金
私たちが支払った住民税は、
以下のような地域の行政サービスの財源として使われます。
- ゴミの回収や公園の整備
- 地域の小中学校・図書館の運営
- 防災・福祉・子育て支援など
つまり住民税は、自分の暮らしを直接支える税金でもあるんです。
✅ 全国民が対象(一定所得がある人)
- 給与所得・事業所得などのある人(パート・アルバイト含む)
- 所得が一定以上(基礎控除後、年収100万円〜前後)
※前年の所得がゼロの人や、扶養の範囲内のパート主婦は非課税になることもあります。
✅ 都道府県民税+市町村民税の“セット”
住民税は2種類に分かれています。
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 都道府県民税 | 県に納める税金(広域行政) |
| 市町村民税 | 市区町村に納める税金(生活密着) |
👉 合わせて「住民税」として一括で徴収されるのが一般的です。
✅ 所得に応じて金額が決まり、
✅ 自分の暮らす“まちづくり”に使われている
──それが、住民税の正体なんですね。
所得税との違いってなに?
「住民税と所得税って、何がどう違うの?」
──同じ“稼いだら払う税金”でも、実はいろんな違いがあります。
✅ 比較表でサクッとチェック!
| 項目 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 納める先 | 国(国税) | 自治体(都道府県+市区町村) |
| 税率の仕組み | 累進課税(所得が多いほど高くなる) | 一律税率(基本10%) |
| 決まるタイミング | その年の所得に対して課税される | 前年の所得に対して翌年に課税 |
| 控除の内容 | 各種控除が細かく設定されている | 所得税より少なめ |
| 納付方法 | 給与天引き or 確定申告 | 給与天引き(特別徴収)or 普通徴収 |
✅ ポイント①:税率が違う
- 所得税:5〜45%まで段階的にアップ(累進課税)
- 住民税:一律10%(所得割)+定額(均等割)
👉 高所得者ほど、所得税のインパクトは大きくなります。
✅ ポイント②:“翌年課税”が住民税の大きな特徴
住民税は、前年の所得に応じて翌年6月〜翌年5月まで課税されます。
たとえば2024年にたくさん稼ぐと、
2025年6月からの住民税がガツンと上がる──これが住民税の“タイムラグ構造”なんですね。
✅ 同じ「所得にかかる税」でも、
税率・タイミング・納付先がぜんぜん違うのが、住民税と所得税のポイントです。
住民税の計算方法はどうなってる?
「住民税って、なにをどう計算して決めてるの?」
──ここでは、住民税の仕組みをシンプルに分解してみましょう。
✅ 住民税は「2つの要素」でできている
| 名称 | 内容 | 課税額の目安 |
|---|---|---|
| 所得割 | 前年の所得に対してかかる10%前後 | 所得に比例して変動 |
| 均等割 | 所得に関係なく定額でかかる部分 | 年額5,000〜6,000円前後 |
👉 この2つを合計した金額が“住民税”になります。
✅ 所得割のざっくり計算式(簡易版)
課税所得 × 約10%(自治体によって若干異なる)+均等割たとえば…
- 年収400万円(課税所得300万円)なら
→ 約30万円 × 10% = 30,000円(所得割)
→ これに均等割(例:5,000円)を加えると
→ 住民税:約35,000円/年
✅ 所得控除によって金額は変わる
住民税にも、以下のような所得控除が適用されます。
- 基礎控除(43万円)
- 配偶者控除・扶養控除
- 社会保険料控除・医療費控除 など
👉 所得が同じでも、扶養人数や保険料の額によって最終的な住民税は変わるんです。
✅ 「一律10%だから簡単」ではなく、
控除や定額分も組み合わさった“ミックス計算”なのが、住民税の特徴です。
住民税はどうやって払うの?
「住民税って、自分で払ってるの?それとも天引き?」
──実は、働き方によって納付方法が違うんです。
✅ 会社員(給与所得者)は“特別徴収”
- 勤務先が住民税を毎月の給料から“天引き”して、自治体に納付
- 通常、6月〜翌年5月までの12回払い(月割)
👉 多くの人が「6月から手取りが減る」と感じるのはこれ!
✅ 自営業やフリーランスは“普通徴収”
- 自分で納付書を使って、年4回に分けて支払う(6月・8月・10月・翌年1月など)
- コンビニ払いや口座振替も可能
👉 自分で納付するぶん、支払いを忘れないよう注意!
✅ “前年の所得”が翌年にくる理由
住民税は、毎年【6月スタート】で【前年の所得】に課税されます。
たとえば:
- 2024年にたくさん働いて収入UP
→ 2025年6月からの住民税が大幅UP
👉 これを知らずにいると、「突然増えた…!」と感じる人も多いんです。
✅ ポイントは「住民税は翌年にくる」
→ 収入が増えた翌年こそ“注意が必要”ということなんですね。
住民税で“損する人”の特徴と対策
「なんか住民税、高くない…?」
そう感じる人の中には、知らずに損しているケースもあります。
✅ ① ボーナスや副業で“年収が急に増えた”人
前年よりも収入が上がると、
翌年の住民税もそれに比例して大きく増加します。
👉 「生活レベルを上げすぎて、翌年しんどい…」というパターンも要注意!
✅ ② 副業やバイト収入を“申告していない”人
副業の収入を申告しないと、
自治体から「会社にバレるような形で住民税が増える」ことがあります。
👉 特に副業が会社にバレたくない人は【住民税の“普通徴収”で申告】するのが安全策。
✅ ③ 退職・転職後の“住民税を忘れていた”人
前年の収入に対する住民税は、
たとえ無職になっても【翌年は発生】します。
👉 退職後も「前年分の住民税が4期に分けて請求される」ことを忘れずに!
✅ 対策まとめ
- 収入UPした年は“翌年の住民税”に備える
- 副業は住民税の納付方法も気をつける
- 退職時は「来年の請求がある」と心得ておく
✅ 知らないと“急な出費”になる住民税も、
「知っていれば備えられる」=損しない働き方と家計管理ができるんです。
まとめ:住民税を知れば“急な出費”も怖くない
「なんでこんなに住民税高いの?」
「いつの間に引かれてたんだろう…?」
そんな疑問や不満は、
“住民税の仕組み”を知ることで、ちゃんと納得できるようになります。
この記事では、
- 住民税とはどんな税金か?
- 所得税との違い
- どうやって金額が決まるのか?
- 納付のタイミングと注意点
- 損しないための対策と心構え
を、やさしく解説してきました。
✅ ポイントは「前年の所得に応じて、翌年課税される」ということ。
✅ 知らなければ驚く。でも知っていれば、ちゃんと備えられる。
住民税は避けられないけど、
“予測できる税金”でもあります。
だからこそ、
- 収入が上がったとき
- 退職・転職したとき
- 副業を始めたとき
に「来年の住民税はどうなるか?」を意識できれば、
家計の急な出費にも振り回されずにすむはずです。
この記事が、
あなたの「住民税、よくわからん…」というモヤモヤを
「ちゃんと理解できた!」という安心に変えるきっかけになれば嬉しいです。

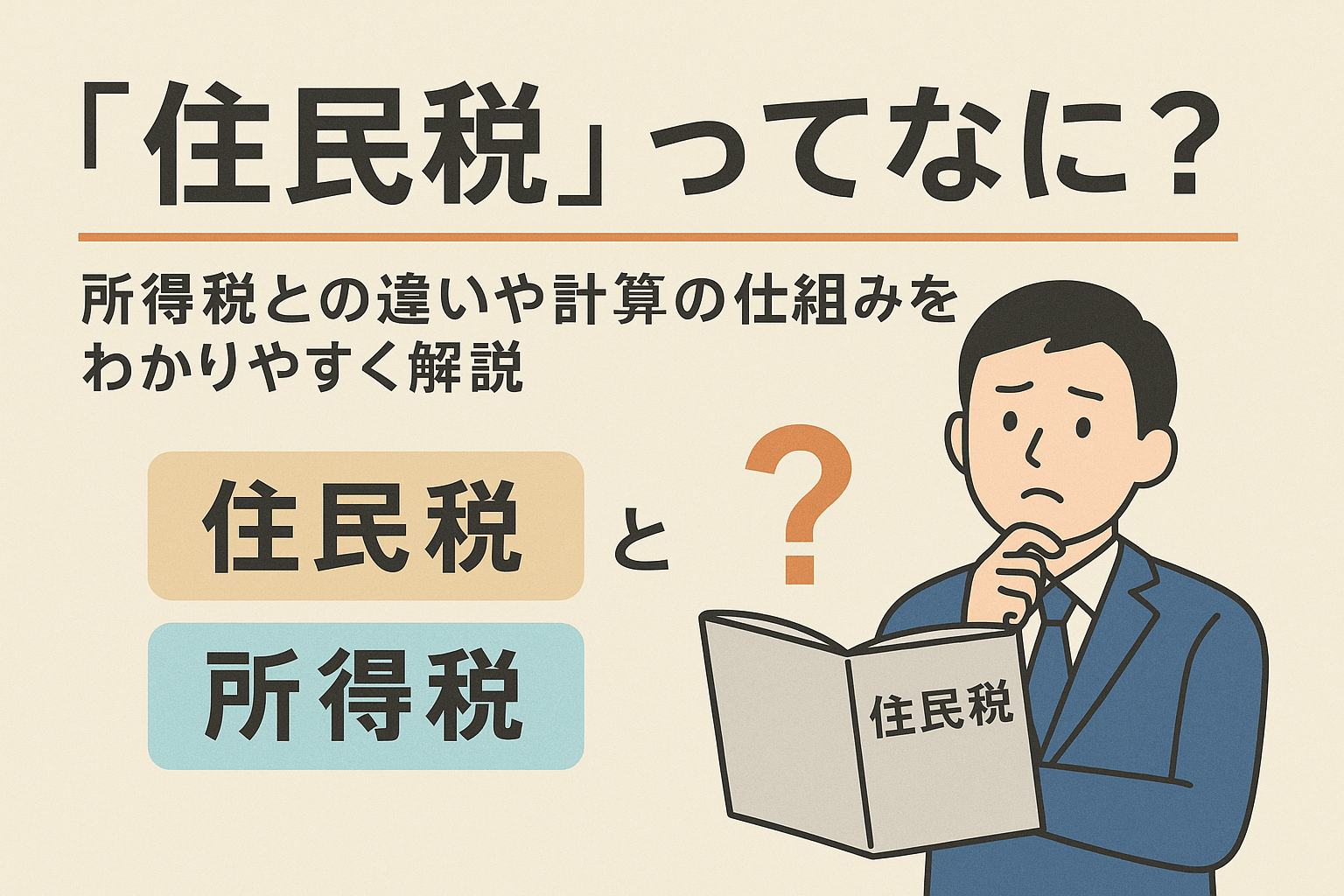

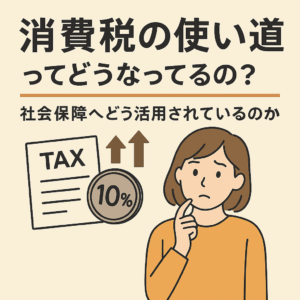
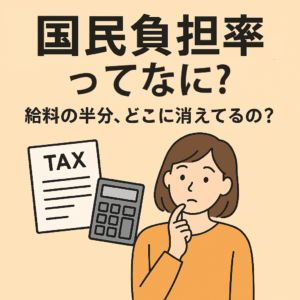
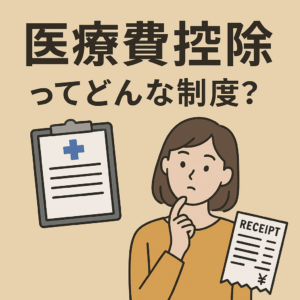
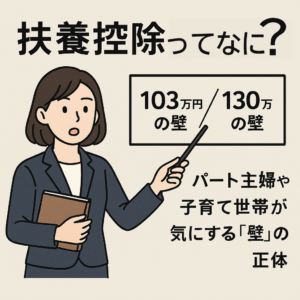
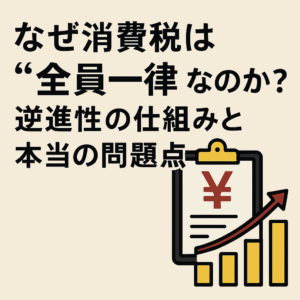
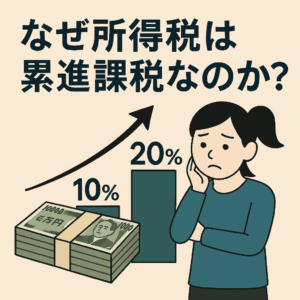
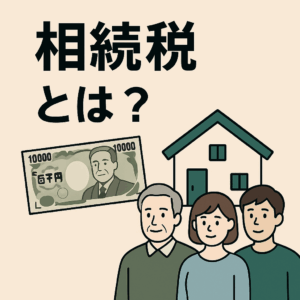
コメント